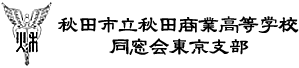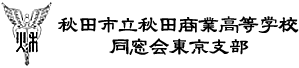2010東雄句会
12月 投句より
冬蛙黒目を張りてみじろがず 千秋
師走入今日も一通喪の葉書 善朗
四阿に腰を据ゑたり紅葉狩 禮泉
穭田に昨夜の雨の残りけり 淳子
試みて量持て余す干菜かな 一灯
釣り人の皆目深なり冬帽子
木漏れ日に一輪傾ぎ山竜胆 菫
日の沈む闇に浮き立つ冬すすき
拳まだ小さく雨の花八手 素風
凩や一両電車北上す
四阿→アズマヤ 穭田→ヒツジダ
2006からこのページに投句の一部を紹介して早5年。
長かったと感じない・・・よく若い人がアッと言う間でした!と言うけれど、それとはちょっと違うような、記憶がポロポロと抜け落ちて時間の経過を実感できない、そんな気がして・・・恐い。
来年こそ日々を大切にするぞ!
助けられ助けられして年暮るる 素風
ツブヤキでも1句できるのです。
このページを見てくださっている皆様へ気楽に俳句を作ってみませんか・・・
会報に掲載される五句抄欄の事務局素風までご連絡を・・・女性陣の入会大歓迎です。
それでは、皆様良いお年をお迎え下さい。 へばまた(*^0^*)/~
11月吟行句会より
 11月14・15日 房総の野島崎へ吟行旅行にでかけました 11月14・15日 房総の野島崎へ吟行旅行にでかけました
小流に傾ぎかぶさり枯尾花 千秋
抱くもあり手を引くもあり七五三 善朗
崖下の小祠閉ざされ秋の風
古城跡里見の里の石蕗の花 陽一
白浜の沖にタンカー小春凪 東潟
日曜の漁師だまりの焚火かな 素風
ひと叢の芒は低く潮じめり
わたつみの声聞こえるか枇杷の花
天気予報では午後から雨となっていましたが
晴れ女3人と晴れ男5人?のおかげで2日間とも好天に恵まれ
暖かな冬の旅を楽しんで来ました。
吟行句は推敲時間が限られていますので、句をまとめるのが
難儀なところですが、見たまま聞こえたまま感じたままを素直に句にすることが
成功するようです。
へばまた(*^0^*)/~
10月投句より
曳き売りのラッパくぐもり秋ついり 千秋
目鼻なき案山子突っ立つ棚田かな
天高し肩で息するゴールの児 善朗
包丁の峯叩きこみ南瓜切る
鶏頭を活ける鋏に種はじけ 菫
実の陰に棘を潜めて柚子蒼し 朴水
霧の粒まとふ湿原鎮まりぬ 素風
団栗に頬ふくらませ栗鼠走る
水澄むや山女魚の影を見失ふ
尾根走る雲秋天に解け消ゆる
秋の季語・・・秋ついり
秋の長雨が梅雨の頃のようなので
案山子
天高し
南瓜
鶏頭
柚子
霧
団栗
水澄む
秋天
11月14~15日は恒例の秋の吟行旅行です。
吟行地は千葉・白浜野島崎です。
自然の中で作る俳句は臨場感あふれる佳句が得られる・・・予定です。
へばまた(*^0^*)/~
9月投句より
鐘楼跡石段残りちちろ鳴く 千秋
窓を開け風入れ厨今朝の秋 善朗
涼気立つ跪座の祈りの大モスク
構内に響く虫の音終電車 陽一
群青の海に真夏日落ちにけり 東潟
零しては穂先の伸びる百日紅 菫
風細く樹下に二頭の黒揚羽
暮れ際の篝火灯る鵜飼川
ままごとは遠き日のこと草の花 耿甫
竿燈や差し手の上で揺らぎ立ち 幹生
9月の句会は7月に亡くなられた沙六氏を偲んで沙六追悼句会として、東銀座JJK会館にて開催致しました。
それぞれに追悼句1句を発表。
蛍火の大きく光り消えにけり 千秋
荒野駆けし兵の通夜大暑かな 善朗
沙六翁逝くや狭庭の百日紅 陽一
外連なく古武士然とし冬薔薇 一灯
去年の秋句会に在りし沙六翁 禮泉
沙六作机上に句集秋灯下 淳子
師の笑顔入道雲となりにけり 東潟
記念誌に想ひあらため夏悼む 菫
九十翁逝きて侘びしき秋句会 耿甫
沙六師を偲び集ひて秋句会 三奏
行く夏に詩魂を説きし人悼む 幹生
瑰や文字に気骨の跡残し 素風
8月投句より
木漏れ日のさす林道や蟬時雨 千秋
先達の通夜の帰りや遠花火 陽一
嫣然と灼熱のなか凌霄花 一灯
朝顔の萎めばすべて同じ顔
トンネルを風にはこばれ夏の蝶 菫
紺碧の海原はるか雲の峰 耿甫
片蔭を選りて承知の遠回り
かき氷食みて幼子眼を瞠る 幹生
噴水の飛沫の彼方幼き日
夏の野に慕ひし星のひとつ落つ 素風
7月22日 我が東雄句会創立時から携わる秋12期渡辺善一氏 俳号 渡辺沙六氏が亡くなりました。
東雄句会は最後の大きな星を失いました。
東雄句会20周年記念句集をお元気なうちに発行でき昨年11月には、真鶴吟行旅行にご一緒できたこと・・・なによりでした。
熱海の夜心底笑ひ蚯蚓鳴く 沙六
7月投句より
雨傘も彩り添へる菖蒲園 禮泉
合歓の花付け睫ごと咲き揃ひ 禮泉
花菖蒲活け出かけたり手術の日 禮泉
大木の先まで絡み凌霄花 禮泉
故郷の青田青田の水豊か 一灯
古稀の会恩師祝ひの夏神楽 一灯
通り雨弾く葉の先青蛙 菫
お下がりの顎ひも弛む夏帽子 菫
この年も半ばを過ぎて半夏生 幹生
くちなしの香り漂ふ夜の道 三奏
夏椿ほのと紅差す蕾かな 淳子
鎮もらぬ熱を残して夕立去る 素風
※凌霄花→ノウゼン・ノウゼンカ 5・7・5 にあわせ
ノウゼンと詠みノウゼンカとも詠みます。
俳句はリズムを大切にします。
へば(*~=~*)また
6月投句より
逆さ富士乱るる山湖青嵐 沙六
あぢさいの茎伸び色のつき初むる 千秋
白ばらの垣を巡らしナース寮 善朗
ひもすがら行々子鳴き暮れにけり 耿甫
新緑や七堂伽藍を呑み込めり 耿甫
木道の行き交ふ鈴音夏は来ぬ 菫
草若葉眺めつ踏みつ野道ゆく 幹生
駿河路の友より届き新茶汲む 幹生
芍薬のまん丸蕾今日ほぐれ 淳子
※ 行々子(ギョウギョウシ)→鳴き声からついたヨシキリの異称
夏の季語となります
へば(*~-~*)/~また
 5月投句より 5月投句より
我が狭庭のハンショウヅル
汐入り池伸び縮みして水母浮く 千秋
対岸に雉子高鳴き夕暮るる
枝撓むばかりに膨らむおほでまり 善朗
風に舞ひ地を転び行く落花かな 耿甫
父母逝きしふる里遠き暮春かな
八十八夜汝と連れ添ひし五十年
天守閣より見下ろせり花の雲 禮泉
江戸川を借景の庭や藤まつり 幹生
鯉幟垂れて遊ぶ子纏ひけり 陽一
茎立つや家庭菜園雨上がり 淳子
大麦の穂の立ち揃ふ越前路 素風
山芽吹き清浄たるや永平寺
※水母→クラゲ 雉子→キギス 転ぶ→マロブ
俳句の世界では花と言えば桜のことを言います。落花と言えば桜が散ることを言います。
なにかと約束事が多いのでやっかいですが、一句づつ作っていくうちに覚えていくのも楽しいところです。
6月19日東京雄水会総会を楽しみにこのへんで へば(*~-~*)また 素風
4月投句より
4月は東雄句会総会を兼ねて集合句会の開催となります。
写真は我東雄句会のおなじみのメンバー
赤シャツは大川善朗会長…かけ声ひとつ…「まずはビールだべ」
なにをさておき、ビールで乾杯!
ぐいっと飲みほし句会の始まり…こんな句会などめったにありません…と思います。
途中でおかわりの注文、さすがに事務局の私はストップを、しかし駄々っ子のごとく
お変わり注文…マ、イイカ!
  
(写真をクリックすると大きなサイズでご覧になれます。)
隠沼に羽打ちのしぶき春の鴨 千秋
黄砂来る曠野に戦友焼ける日も 沙六
海鞘切れば磯の香放ち汁飛べり 善朗
長閑さや番山鳩羽繕い 陽一
車座に椅子席もあり花の宴 一灯
抹茶点て志野の菓子鉢蓬餅 淳子
花見酒老木の根に分けてやり 東潟
瀬を奔り浮きつ沈みつ花筏 耿甫
ひとり観る夜の桜の寂しさよ 三奏
ボート浮く淵をめぐるや花の雲 素風
欠席投句
一雨にミモザの花のくすみけり 禮泉
椅子の数増えて夕餉の蜆汁 菫
春天にとどけ母校歌甲子園 幹生
4月3日は花冷えの日が続く中、好天にめぐまれて最高齢の渡辺沙六さんも
ステッキをたよりに出席されました。
黄砂来る曠野に戦友焼ける日も 沙六
…の1句は内容が濃く重たいものでした。桜の時期と戦争は何故か重なる
日本人の感慨。しかし、このような句を実感をともなって作れる先輩はだんだん
少なくなります。
ビールで乾杯からはじまった4月の集合句会はこの1句でピシリと締まりました。
※隠沼コモリヌ ※海鞘ホヤ ※番ツガイ
ヘバ(*^_^*)また 素風
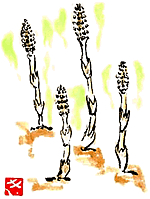 3月投句より 3月投句より
妻米寿祝ふや春の京料理 沙六
鳥海の肩より帰雁砂丘飛ぶ
池の上二三周鴨半ば引く
啓蟄や野小屋の軒に農暦 千秋
白梅をあらかた散らし昨夜の雨 善朗
天神や梅綻びて絵馬の山 禮泉
春一番庭の如雨露を素っ飛ばす
新枝のすべて垂れをり柳かな 一灯
湯気の立つ薦の外され春の苑 陽一
長閑さや最南端でバスを待ち
箱を出し納むも雛に話しかけ 素風
※昨夜ヨベと詠みます
早春賦の歌詞(作詞吉丸一昌)の世界を肌で感じるこの季節、今年の春はとくに麗らかな日が少なく時間ばかりが過ぎて、
4月を迎えています。
東雄句会には新入会員が1人ありました…現在13人となり、新鮮な風が吹いてくれることを期待したいと思います。
へば(*^-^*)また
2月投句より
ガスタンク巨球一点冬日照る 沙六
凍雲をかかげ朝富士屹立す 千秋
出揃ひて産毛の光る辛夷の芽
冬帽の郵便バイク山路行く
枝寄せて探る香りの梅二輪 一灯
寒気裂き修行僧列成して行く 陽一
春の雪鹿の子斑に残る土手 素風
春は名のみの風の寒さよ・・・と、立春を過ぎるころに雪がふったり気温の低い日が
続いたりで、目の前の春がなかなか近寄ってくれません。
俳句には
春近し・春隣・・・とどこかに春を感じとる冬の季語があります。
万物が動きだす春は待ち遠しいものです。
東雄句会では会員の募集を随時受け付けています。
現在12名(3月から13名)の会員で俳句を楽しんでいます。
◎女性会員は高11期・高17期・高19期の3名です。なんとか女性会員を増やしたいと願っております・・・
初心者の方には選者(千秋)が親切丁寧な添削指導をして下さいます。
仲良し仲間の楽しい句会はいかがでしょうか!!!
へば(*^-^*)また
1月投句より
新年おめでとうございます
※俳句は歳時記をもとに季語をひとつ入れて5・7・5をまとめますが春夏秋冬そして特別に新年という特別の季語があります。
手風もて香煙を寄せ初詣 沙六
門松や屋並の低き蔵の町 千秋
発熱の子の看病や除夜の鐘 禮泉
励ましの一句添へあり師の賀状 一灯
凧揚げや犬も子供も皆走り 東潟
一村を煙に包み夕焚火 菫
今年の冬は故郷秋田は大雪で、年末から「雪掻きをしねばねくて大変だぁ~」と聞こえてきました。
考えてみれば我が友人達も還暦をこえて大変だぁ~も切実な感あり・・・
さて、今年も俳句作りに精進いたします。どうぞ宜しく御願い致します。 へば(*^-^*)また
2009東雄句会
12月投句より
黒潮の真っ赤や伊豆の冬日の出 沙六
谷地坊主一つ一つに雪積る 千秋
朝市や水流しつつ鰤さばく
ビル狭間暮るれば白き冬の月 耿甫
初島へ小春の海の定期船 淳子
狛犬の頭に鎮座濡れ落葉 三奏
街路樹に光の粒着せ十二月 素風
東京雄水会のHPが新しく生まれかわる間、11月からお休みしていました東雄句会の、毎月の句会便りを再会することができました。
担当幹事の皆様ご苦労さまでした。そしてありがとう御座いました。
引き続き、毎月の句会便りを掲載させていただきます。
へば(*^-^*)また
11月投句より
11月8~9日真鶴へ吟行(一泊)旅行
その場で俳句を作る楽しさと難しさ・・・句会のあとの懇親会がさらに楽しいので毎回出席者は多数です。
初島を望み昼餉や秋うらら 千秋
水仙の芽生えの続き崖石階 沙六
断崖に浜木綿すがれ三ツ岩礁
真鶴や樹下に明かし石路の花 善朗
触るること叶はぬ蔓の零余子かな
満席のバス岬まで小春かな
原始林残る半島冬山路 陽一
一村を懐に入れ山眠る 一灯
冬の波一直線に迫り来る 禮泉
三ツ石の岬巡りや海桐(とべら)の実 淳子
吾が胸の高鳴り押さへ秋の海 東潟
潮騒を目をとじて聴く秋の暮れ 菫
浦里や山肌に沿ふ蜜柑畑 素風
冬ぬくし蟹は藻を食ふ潮だまり
へば(*^-^*)また
10月投句より
青天の湖岸紅曼珠沙華 沙六
触れ合ひて宙に口開け通草の実 善朗
手にあふる葡萄の房の重さかな 耿甫
語る妻あり安らけき良夜かな 耿甫
実紫雫を溜めて枝撓ふ 淳子
※今年の仲秋の名月は10月3日でした。夜分には雨もあがり見事な満月を見ることができました。月はそれを見上げる人の事情で様々な思いを与えてくれる不思議な宇宙の星の一つです。
そして多分地球から見る月が一番美しいのだと思います。
名月や池をめぐりて夜もすがら 芭蕉
いつの日か、私も佳い句が出来ますよう精進しましょう。
へば(*^_^*)また
9月投句より
輪の外に手だけの踊り老爺立つ 沙六
入札のベル鳴る糶場初さんま 千秋
源泉の湯煙流れ岩燕 千秋
虹二重太平洋を跨ぐかに 善朗
湯上がりの白き襟足藍浴衣 耿甫
傾きし案山子の残る棚田かな 禮泉
朝顔の明日咲く蕾数へをり 淳子
※ 俳句では踊りといえば盆踊りを言います。夏の季語。
今年の夏は静々と過ぎていったような気がします。我が家では庭の水撒きを一回もしませんでした。ショボショボと雨の日が多く、庭土がカラカラに乾くことがありませんでした。
十月に入って既に5日となりましたが今日の気温は低く曇り、秋空は長く続かないです。それでも先日の満月は午前中までの雨が上がり高い夜空に耿々と輝いていました。
ヘば(*^_^*)また
8月投句より
左右の足踏み替へ進む阿波踊り 千秋
独り酌む小半酒や冷奴 善朗
かなかなの鳴いて仕舞の鍬洗ふ 一灯
落蝉やもてば未だある力かな 菫
風立ちて音なく寄せる青田波 耿甫
べた凪の稲田の蒸れる大暑かな 耿甫
病む友に言葉選びて暑気見舞い 素風
※小半酒(こなからざけ)=半分の半分つまり二合五勺の酒または少量の酒
台風11号が銚子沖を北上していきました。おかげで今日は肌寒いど・・・
然し、明日はまた残暑が戻るとか、体調管理のほどお願い致します。
へば(*^_^*)また
7月投句より
梅雨晴間白蝶速み道路越ゆ 沙六
滝行場閉ぢ蝋燭の灯しあり 千秋
一鍬に探る今年の馬鈴薯の出来 一灯
拍手湧く子鴨やうやう群れに着き 一灯
糠床の指の腹刺す茄子の刺 菫
※馬鈴薯=ジャガと読みます。
故郷秋田は、今夏雨が多く冷夏の予報が伝えられ、お米の出来具合が心配されます。そのような不安定な天候中、私の故郷土崎の港祭りは無事に終わり、またTVのニュースでは竿燈も天気にめぐまれたようで何よりでした。
この季節、暑さで食欲が減少すると、真っ青に漬けあがった茄子の塩漬けと、お水をぶっかけた冷や御飯でガブガブとお昼をすませた昔を思い出します。当時はそんなお昼御飯も当たり前でしたが、上京後は行儀の悪い事だし貧しい食事かも知れないと他言無用で
した。今飽食の時代には懐かしく、あれも良しかも・・・と思うのです。
秋田の茄子がっこいがったな~!!!
6月投句より
望郷やすかんぽの酸の淡ければ 沙六
激つ瀬に光り反転柳鮠 千秋
夕映えの能登の棚田や海一望 禮泉
未央柳蕊に雨滴をとどめをり 禮泉
紫陽花の色付く前の一枝活く 淳子
行く先の確かにあるや蟻の列 素風
※ 柳鮠(ヤナギバエ)ハヤ・ウグイの別称 未央柳(ビョウヤナギ)
梅雨の季節の最中ですが・・・
梅雨期の初めに吹く南からの湿った風を俳句では黒南風(クロハエ)といいます。そして、梅雨明けの頃に吹く風を白南風(シラハエ)といっております。風の呼び方には数知れずの言葉があるようで、日本語の難しさおもしろ
さに感銘するのです。ちなみに私は素風という俳号に自己満足しているのです。
へば(*^_^*)また
6月20日 東京雄水会総会に出席いたしました折り、新校長先生のご挨拶が有りました。その中で校内の挨拶が整然とできていることに感動されたそうです。新校長先生は秋商の卒業生ではありませんので、驚かれたようです。
そのお話を聞いて、私は嬉しかったです・・・3年間で身についた挨拶の習慣は社会人になって一番役にたったことでしたから、今でも後輩達に引き継がれていることが何より!と思いました。 素風
5月投句より
黄帽子の行列乱す若葉雨 一灯
今月は点が割れました。その中からピカいちが掲句でした。
一灯さんおめでとう御座います。
6月20日は東京雄水会の集いが開催されますが、その折りに俳句に興味の有る方チョットお声をかけてください。東雄句会20周年記念の句集を読んで見たい方には、残り僅かですが持参いたしますので差し上げます。素風
へば(*^_^*)またネ
4月投句より
大陸の戦野をまざと黄砂の天 沙六
棟上げの木槌の音や春半ば 善朗
薄紅を花心に秘めて花辛夷 耿甫
未練てふものは持たずや巣立ち鳥 素風
見上ぐれば花降るごとく枝垂れける 素風
例年のとおり東雄句会の総会も無事終わり、懇親会もいつもどおり和気あいあい・・・すっかり家族や兄弟のような雰囲気を感じて、善し悪しかなぁ~とも思います。
新会員が入会してくれることを切望して止まない我が東雄句会です。
確実に平均年齢が高くなって、それはそれで結構なことですが・・・ネ
へば(*^_^*)またネ
3月投句より
春暁や漁船沖より灯し来る 沙六
つくばひを溢れこぼるる春の水 千秋
潮垂るる若布干しあり漁師小屋 千秋
老いの手を曳くも老いの手梅見かな 善朗
幹朽ちて苔むす古木梅咲けり 善朗
病癒え嫁ぐ娘や雛飾る 一灯
伊豆急線窓一杯に春の海 淳子
春を感じながら、桜が咲かないと春が来たと思えない、日本人の心。
少し掲載が遅くなりましたが、只今は桜前線直下となりました。
老いの手を曳くも老いの手梅見かな 善朗
実はこの句をとりませんでした。老いの手を老いの手が曳くは…老老介護?つらいなぁ~と思えたからでした。ところが、つい先日私の大分前を手を繋ぎあって肩寄せ合って歩く老夫婦の姿を後ろから拝見。追いついて追い越す頃には、そのお二人の会話まで聞こえヒソヒソと笑い合ってゆっくりゆっくり散歩している様子が判りました。楽しそうで、「仲がが宜しくて結構ですネ…」と声をかけましたら、老婦人(奥様)が笑いながら「私が手を離すとこの人(ご主人)は転んじゃうんですよ」と。ご主人様は片方の手にステッキを使い、お身体が不自由のご様子。そしてご主人笑いながら曰く、「手を繋ぎながら喧嘩もするんです」とおっしゃいました。背丈はお二人とも同じ程、小柄なお二人が肩を寄せ合うように路地に面した庭の花を愛でながらリハビリ中のお散歩でした。心がポッと暖かくなりました。
へば(*^_^*)またネ
2月 投句より
雪原に鹿の目光り夕間暮れ 千秋
朝富士を仰ぐ峠や初音聞く 千秋
雲ひとつなき大空に凧揚がる 淳子
埋み火のごとくありしや遺句読めば 素風
水仙に凜といふ氣をもらひけり 素風
東雄句会20周年の記念行事は無事に終了・・・記念句集はとても評判がよく、お褒めの言葉もあちこちからいただいております。
我が母校秋商は俳句作りの盛んな時代を歴史に持ち、現在に至っているわけですが、母校繋がりで卒業生が句会を持ち俳句活動を続けていることは珍しいことのようです。
東雄句会創立20年を越えあらたに21年を歩き出しました。この句会の灯を消さぬようつづけていきたいと念じています。
勿論、新会員の入会があっての継続です。どうぞ、恐れず躊躇せず入会の勇気をふるってお申し込み下さい。
東雄句会はいつでも歓迎です。
へば(*^_^*)またネ
1月投句より
青天や三代集ふお元日 沙六
山門に紫幕めぐらし年用意 千秋
初漁や波切り競ひ出港す 千秋
一望の海も染めたる初茜 禮泉
鯛下げて賀状に友の古稀の顔 一灯
新年を迎えていつもながらあっという間に一月も下旬・・・節分が目の前です。故郷秋田は寒いだろうなァ~と暖かい土地に少しばかりの後ろめたさを感じつつ過ごす季節です。
昨年の12月で東雄句会は20周年を迎えました。創立当時からの大先輩がお一人矍鑠と御健吟されて、この度の記念句集発刊にさいしては大いなる力を貸して下さいました。
この記念句集も立派な仕上がりで、ご希望の雄水会会員様には謹呈させて頂きますので、卒期とお名前住所をお知らせ下さい。
東雄句会事務局 松岡 素風
住所・電話は東京雄水会会報・五句抄のページに記載されております。
又、6月の総会会場にてその由、声をお掛け下さい。
本年もまた一年、この東雄句会のページにお付き合い下さいませ。
へば(*^_^*)またネ
TOPへ戻る
これ以前の作品はこちら
|