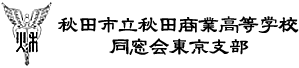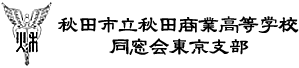2009年の作品に戻る
2008東雄句会
12月 投句より
躙口開け昼灯す紅葉茶屋 千秋
蔓引けば藪さざめきて烏瓜 菫
大錨錆付き置かれ冬の浜 陽一
散り散りて山茶花なほも花盛り 沙六
洩れ聞こゆ琴の調べや菊日和 耿甫
冬茜雲の端染めて広がれり 素風
一年も暮れようとしています。
私事ながら、私の還暦という大きな節目も早賞味期限がおわろうとしています。さて、東雄句会は創立20年、記念の句集を編集してみて、私は、大先輩達が大切に育んできたこの句会から、俳句の上達はさておき、母校秋商つながりと言う強く暖かな絆を頂いていることに改めて、感謝しています。
この句会をとおして私が得られている大切な経験を、もっと多くの後輩達に引き継いで頂きたいと心からおもいます。俳句を作ることに抵抗があるかもしれません・・・しかし俳句という詩心はあとからでも良いのです。東雄句会は秋商つながりの人間の輪です。
昨今の世情を思うとき、せめてこのつながりを大切にしていきたいと強く思うのです。
私の恩師、高島清子先生が詠んで下さった短歌ですが
教え子よ
東京砂漠のなかに居て
母校を恋うる日はなかりしか
があります。
このHPのこのページを見て下さっている後輩の方々に母校秋商のつながりは、いつでも皆様を待っていることを
東雄句会を通してのメッセージと致します。
それでは へばまた(*^_^*)来年 素風
11月 日光吟行句会より
我が東雄句会はこの12月に創立20周年を迎えます。そこで11月の句会は記念行事の一つとして日光へ吟行1泊旅行へとくりだしました。東照宮はもとより二荒山神社などを巡りながらの吟行です。
当日11月9日の朝、東武浅草駅集合
今朝の冬駅に集ひし馴染み顔 陽一
車中から吟行は始まります。紅葉に色づく世界遺産を巡りながらの作句でした。夜は宿にて作句をもとに句会で
す。
その中から高得点のはいった句を披露いたします。
山宿の板塀伝ひ蔦紅葉 千秋
日光線刈田の果ての杉並木 善朗
神苑を流る禊の水澄めり 耿甫
滝壺の底に重なり散り紅葉 耿甫
朴落葉敷きて頬張る握り飯 素風
紅葉づける山梵鐘の音しむる 素風
冬立つや山懐に朱の御堂 素風
句会のあとはいつものお楽しみで、一献傾けながらの懇親会です。黄葉・紅葉の美しさを喜びながらお湯につかり、良い一日を楽しみました。翌日は川下りをしながら、また作句に励み帰りの電車内で句の披露でした。
記念行事のもう一つである記念句集の編集も順調に進み、来年早々に記念句集発刊祝賀会を予定しております。
なにをさておいても諸先輩方の熱き心が土台になっていることを再認識致しております。
それでは へばまた(*^_^*)V
10月投句より
さみどりの川藻の靡き水澄めり 千秋
まつたけと朱書きの幟道の駅 千秋
かろやかに落葉踏む音森の朝 二郎
柿剥けばのの字に皮の繋がれり 耿甫
摩周湖の逆さ紅葉の湖面かな 陽一
丈高き壺に真っ直ぐ芒活く 淳子
秋高し五百人の太極拳 一灯
虫すだく時に休符のあるリズム 素風
10月も月末になってようやく、夜長を楽しむ為に、羽織るものが欲しい気温になりました。
今年は季語「秋暑し」の出番がありそうでしたが・・・ゼロでした。
秋は長雨の季節でもあります。その雨が降り続く中、我が敬愛する友人が亡くなりました。秋商を愛し雄水会を愛した友人でした。
母校愛つよき友逝く秋時雨 素風
それでは、へばまた(*^_^*)
9月投句より
女将連浴衣きりりと踊りけり 沙六
蜩の声渓に聞き尾根を行く 千秋
灯台へ登る坂道蝉時雨 千秋
緑陰に跪座の放牛動かざる 善朗
川向う消えて音する遠花火 耿甫
庭園にカンツォーネ聞く晩夏かな 素風
白金の光りさざめく芒原 素風
涼風が立つと昨日までの暑い日々が嘘のように遠くに感じられます。
蝉の声が虫の声にかわり自然の移り変わりは正直ですね。
蝉時雨・虫時雨・・・俳句ならではの言葉です。
ところで、セミという漢字は蝉ではなく虫ヘンに單であることをご存知でしょうか?この掲示版では蝉の漢字しか使えませんのでやむを得ず蝉を使いました。
以上です。へばまた(*^_^*)
8月投句より
粒揃ひ棚の撓みや黒葡萄 千秋
夏霞巨船汽笛を交はし行く 千秋
葛の蔓無縁塚へと伸びてをり 二郎
熊笹の繁みぬきんづ鬼薊 善朗
以上です へばまた(*^_^*)
7月投句より
仄暗き天地を分かずさみだるる 耿甫
吊忍茅葺屋根の深庇 千秋
菖蒲守鋏を鳴らし摘みゆけり 千秋
つかの間の白さや沙羅の風に落つ 素風
又来るも去るも揚羽の一花かな 素風
梅雨が明け本格的な夏に入りました。
連日の真夏日に、ここは我慢のしどころと・・・やり過ごし、夏のあとには必ず
涼風の立つ秋がやってくることを楽しみにしているところです。
子供の頃土崎の港祭りは日本一のお祭りダ!と信じていました。
お囃子、踊り、枝豆、カスベなど五感に刻まれた懐かしい思い出が宝ものです。
写真は友人が送ってくれました将軍野二区の曳山(山車)です。
さて、東雄句会は同好会として発足して今年12月で創立20年を迎えす。
只今は同好会員13名、発足当時からの先輩はお一人になってしまいまた。
これからも東雄句会に流れる、睦ましく楽しい雰囲気を大切に守って継続できることを祈ります。
東雄句会はいつでも入会OKです。
アタックしてみてください。
今月はこのへんにて、へばまた(*^_^*)
6月投句より
夕映えの砂丘玫瑰(ハマナス)
燃えに燃ゆ 沙六
秋田・新屋浜にて 浜梨とも言う
断崖の山藤映ゆる峡日和 千秋
鳴き鳴きて声の嗄るらむ葭雀 耿甫
奥山の闇より聞こゆ青葉木菟 素風
以上です。
梅雨の6月・写真は庭の夏椿(沙羅)です。
自然を詠う俳句ですが、山がひとつ消えてしまうほどの天変地異、岩手・宮城大地震にはその凄まじさに言葉もありません。
被害にあわれました地域の皆様にお見舞い申し上げます。
さて、俳句には独特の用語があり、これが解りにくく興味があっても敬遠される原因の一つになっているようです。
なるべく平易な言葉で作句するように心掛けてはいても、5・7・5に納めるために俳句用語の難解漢字等を使わざるを得ない場合があるのです。
掲載句のなかから
葭雀(よしすずめ)→葭切(よしきり・鳥)
青葉木菟→あおばずく(ふくろうの仲間)
俳句を作りながら、先人達の残してくれた美しく細やかな日本語に触れる機会がおおくなります。
東雄句会はいつでも皆様の入会をお待ちしております。
日々の生活の中でふと、5・7・5が頭に浮かんだらまづ、書き留めてください。生活が楽しく豊になります。
今月はこのへんにて・・・へばまた(*^_^*)
5月投句より
たんぽぽや墓誌の刻字の新しき 千秋
泥煙り上げて隠くるる蛙の子 千秋
花木瓜や伏し目におはす地蔵さま 耿甫
一頻り囀りし鳥遠ざかる 禮泉
山毎に万緑尽くし連なれり 素風
見上ぐれば岩つつじ咲く川下り 素風
以上です。
風薫る五月と申しますが、今年はなかなかその様な日が少なく、これからやってくる梅雨の季節や夏の暑さが思いやられます。
俳句は自然を詠むことが主流となっているようです。その自然から季節を感じとって自分の言葉で表現すること、さらにその中に言葉にしない自分の心が詠み手に解ってもらえる・・・と嬉しいですね。 へばまた(*^_^*)
4月集合句会より
・梅林の白の極まりうす青し 沙六
・春障子影やわらかく鳥去れり 二郎
・本流に乗れず花びら淀みたり 二郎
・花桃の咲いてなほ増す白さかな 素風
例年4月には東雄句会の総会を兼ねて集合句会を開きます。
普段は投句句会ですので、皆様と顔をあわせる楽しみで出席者多数となります。句会~総会~懇親会といつもの通り和気あいあい・おしゃべりがとどまるところなし。ただし、句会は別もの・・・。この度は見学者1名を迎え「おっ、入会の期待大かな?」と内心をおさえつつ普段通りの句会をお見せできたと思います。
一年のうち、投句句会・集合句会の他に勉強句会という会も行います。そのような時に見学されて、この東雄句会の雰囲気を体験し入会されるのも一つの方法です。俳句作りに興味がある方はどうぞ、構えずにまづは素風まで、連絡を下さい。
添付写真は3月29日の総会・集合句会の模様です。
3月投句より
・花摘みて房総の春持ち帰る 一灯
・啓蟄や妻やうやくの床払ひ 陽一
・春一番よろけ躓く放ち鶏 千秋
・片頬を撫でる川風春の土手 二郎
俳句には旧仮名遣いを使うのが通例ですが、現代仮名遣いでもよろしいのです。
自分は現代仮名遣いで通します・・・を通してくだされば可です。
3月29日 東雄句会は総会・句会・懇親会を開催致しました。
見学者1名を得てとても和やかに(何時も)楽しみました。4月投句よりとして掲載いたします。
2月投句より
・まん丸の初日揺らぎ出海離る 千秋
・蒼天に屋根より高きミモザかな 淳子
・小春日や雀と共に跳ねてみる 信也
・牡蠣飯や磯の香満ちて炊き上がる 澄子
・いぬふぐり日溜りに群れひとところ 澄子
・抱え来し水仙揺れて香も揺れて 素風
・針持てば白絹まぶし春隣 素風
・空といふ区切り見えぬや牡丹雪 素風
・雪片の細かくなりて降りまさる 素風
立春に雪が降りました。雪は格好の俳句ネタ・・・ところが、なかなか思うような句が生まれません。
『初雪や二の字二の字の下駄の跡』などと楽しい句が多く残されているからでしょう。
暦のうえではもう春です。
俳句は季節を誰よりも早く感じとり、その感動を5・7・5に詠います。
つい、見逃しがちになる季節の移り変わりに注意深くなって生活が豊かになります。鳥の名前、花の名前、風の情況等々、もっと云えば、台所の俎板の上にも季節があります。
一緒に俳句を作りませんか?
楽しい諸先輩方が丁寧に教えて下さいます。 以上
高17期 松岡 素風でした (*^_^*)へば
東雄句会の毎月の投句から、点の多く入った佳句をご紹介しておりましたこの場を、諸般の事情によりしばらくお休み致しておりました。しかし、楽しみにして下さっている由のお声に、年があらたまった1月から再開させて頂くことにしました。何卒宜敷お願い致します。
1月句会より
白髪の増えし長子と年酒くむ 沙六
湿原の暮色や鹿の声響く 千秋
妻と粥啜る七草閑かなり 沙六
ひと通り為すべきを終へ晦日そば 善朗
東雄句会は秋商OBの東京雄水会のメンバーが会員であることはご承知のとおりですが、最高齢の沙六氏は今年卒寿の大先輩です。その後につづき高21期までの13名が、楽しく脳トレしています。俳句はひねると申しますが・・・今風には脳トレでしょうか。
男性10名女性3名です。
男性陣いわく、女性がもっと増えないかなぁ~!と 女性陣いわく、若い男性がどんどん増えないかなぁ~!なんて・・・
東京雄水会のあたたかい雰囲気はこの東雄句会に凝縮されていると言って過言はないと実感いたしております。
只今クラブ活動のページを作成中とのこと、そちらの方へ東雄句会の活動状況や句会への参加の仕方など詳しく掲載して頂きますので、是非ご覧下さい。
また、この句会のご報告は毎月させていただきますのでどうぞお楽しみに。
高17期 松岡素風(女)でした。
2007東雄句会
3月句会より
春暁や一燈マストに帰漁船 沙六
小太鼓の正座の童春祭 一灯
雛の部屋雪洞のみを灯しけり 禮泉
白木蓮枝の限りに溢れ咲く 千秋
4月は年二回の集合句会が開催されます。昨年は新人が1名入会されてとても嬉しい会となりました。
今年も新会員が入会してくれないかなぁ~!
2月句会より
地吹雪を追ふ地吹雪や会津口 沙六
一竿となり沼を発つ小白鳥 千秋
2月投句から傑作が誕生したようです。
沙六さんの地吹雪の句は、会員のほとんどの人が特選として・・・私が知る限りでは今までの最高得点となりました。素晴らしい!
おかげで、今月は他に点数がいかず、掲載点を得た句が少なくなりました。
沙六さんは米寿の大先輩です。
1月句会より
なまはげや惚けし母まで逃げ惑ふ 信也
初護摩の散杖響き火の粉飛ぶ 千秋
鐘遠く聴きつつ列へ除夜詣 沙六
焼き締めの小鉢によそふ柚子なます 淳子
子の帰省する日を待ちてきりたんぽ 淳子
大晦日から新年の句です
2006東雄句会
東雄句会・12月句会より
灰ならす父の寡黙や榾あかり 二郎
店先の激安幟師走かな 陽一
山湖暮れ男体照らす冬の月 千秋
堂古び古刹の庭や冬桜 千秋
村里の墓石の上に散紅葉 淳子
冬ざれや河原に立てり鷺一羽 信也
※榾ホタと読みます。
謹賀新年
サッカーは本当に残念でした!
さて、今年も一年よろしくお付き合い下さいませ。
この掲示板を見たよ!って誰か入会してくれないかなぁ~と期待しています。
11月句会より
11月の句会は先に掲載致しましたとおり吟行句会からの発表となりました。
浜鴫や嘴の沙蚕を咥へ引く 千秋
藻に潜り藻に頭出し二羽の鴨 善朗
秋潮や満ちて入り来る鳥羽屑 陽一
以上の句が多くの点をあつめました。
※嘴はくちばしと読みますが、俳句ではハシとよむことが許されています。※沙蚕はゴカイと読みます。
谷津干潟には川鵜・鴫・鷺・千鳥・鴨・鳰等の可愛らしい鳥達が秋の日差しのなか気持ちよさそうに集まっていました。潟は調度潮が満ちる時間でシオマネキ・鯔・ふっこ・エイなどが満ちてくる潮に見つけることができました。
俳句ネタが沢山落ちていてもなかなか旨く詠めないのが残念です。フッ!
吟行句会は緊張しますが、つい状況にながされて句を作ることを忘れてしまいます。気がつくと〆切時間が近いのに数ができずあわててしまうのです。
吟行→句会→懇親会と本当に楽しい一日でした。雄水会の皆様お仲間になりませんか?会員一同いつでも歓迎いたします。
10月投句より
月見坂のぼり良夜の光堂 沙六
象潟の九十九島や稲の波 淳子
里山の闇深めつつ月のぼる 素風
今月は月の句を沢山ご披露できるかと予想しておりましたら、票ががわれました。
11月は例年でしたら吟行句会となりますが、諸般の都合により10月28日(土)に繰り上げ行いました。
吟行地谷津干潟・・・お天気もよく、楽しい吟行となりました。句会場を八千代台に移しそれぞれの吟行句を出句。
さて、結果は! 11月の掲載をお楽しみに(*^_^*)
9月投句より
紅萩の咲き満ち撓み花こぼす 千秋
鮎釣りの脛にしぶきの荒瀬かな 千秋
経蔵に木立の影を月涼し 沙六
通院の急坂喘ぎ蝉時雨 善朗
甚平の翁定時に雨戸開け 陽一
月時刻糸のほつるる烏瓜 澄子
季節は八百屋さんの店先などにもあらわれます。季節感のなくなった野菜や果物ですが、栗・柿はまだまだ季節限定で、だからというわけではありませんが、とても嬉しい秋の風物です。
さて、10月の投句には月の句があつまることでしょうが、月の句はなかなかに難しいのです・・・。
8月投句より
羅(うすもの)を纏ひ僧侶の大鞄 善朗
尺蠖を咥へなほして雀たつ 素風
玄関に月下美人の香のあふれ 二郎
素焼鉢あふれるほどの日日草 淳子
蝉時雨一匹だに見ず磴のぼる 沙六
さて、秋雨前線がもたらす雨が、大地に残る炎熱までも嘘のように鎮めてくれました。
秋から冬にかけての季節は今だに望郷の思いにかられます。
文化祭・フォークダンス・面影橋から学校までの土手の月見草・etc.
東雄句会の投句には秋田を懐かしむ一句が投句されることもしばしばあります。♪同じ室に咲く雄花♪秋商生でよかった・・・と卒業して40年たっても誇りにおもいます。
東雄句会はそんな仲間の句会です。いつでも入会できます。お待ちしております。
7月投句より
空堀の底を掠めて夏つばめ 二郎
散り沙羅の雨に打たるるままに朽ち 善朗
揺らぐ葉にはりつき揺るる青蛙 素風
長かった今年の梅雨もようやく終わり本格的な夏が幕開けです。夕方には蜩がカナカナと鳴いて、自然界はボヤボヤしていないなぁーとつくづく思います。今夏は甲子園への出場がなくさみしい夏ですが・・・それもアッという間に過ぎて行くのでしょう。その自然の移り変わりを5・7・5にキャッチするのが俳句です。
東雄句会は皆様の入会をいつでも歓迎いたします。
6月投句より
巻きゆるびふふむ蕾や花あやめ 千秋
みず叩き癌道連れの余生かな 善朗
桑熟うる水路静かに手漕ぎ舟 素風
四季折々の雪月花を自分の生活の中から発見し感動し、余分を切り捨て17文字におさめる・・・これが俳句という詩です。5・7・5は日本のリズム
どなたにもつくれる俳句です。
東雄句会は皆様の入会をいつでも歓迎
いたします。
5月投句より
支柱反り腹の膨らむ鯉幟 陽一
空豆やたぎる湯の中泡を吹き 素風
味噌汁に入れて味はう庭の蕗 禮泉
捨舟や沼に出揃ふ葦若葉 千秋
6月3日 ★東京雄水会の集い★出席
若い後輩達の出席が増えて活気を感じる楽しい会であったこと嬉しかったです。武藤氏の講演も気取りがなく、同じ室に咲く雄花♪の感ありで好感がもてました。このしみじみとした感動を来年に繋げたいとおもいます。
今月の投句から…を掲載いたしましたが、ご感想などお寄せ頂ければ今後の励みになりますのでお待ち致しております。東京雄水会・会報にも五句抄欄をもうけていただいて句会員の作句を披露しております。どうぞご鑑賞ください。 17期 松岡悦子
4月集合句会より
諍いのあとの沈黙花吹雪 二郎
摘みとれば棘柔らかき山椒の芽 善朗
枝手折り白磁の壺に桃の花 淳子
春ショール白髪婦人の丸き肩 素風
4月は久し振りにメンバーに会え楽しい句会を過ごしました。
新入会員が一名、新鮮な風をもって入会!これからがとても楽しみです。
東雄句会は随時入会者を募っています。どうぞ躊躇せずに俳句の世界をのぞいてみて下さい。
6月は東京雄水会の集いも開催されます。遠慮無くお声をお掛け下さい。
3月投句より
万蕾の揃ひほぐるる梅の園 千秋
お玉杓子たらひの水も一世界 二郎
色別のパンジー揺るる花時計 素風
などに点が多く入りました。
只今11名の俳句仲間で楽しみながら
頑張っています。
もちろん達者な者からやざかね者まで和気あいあい!他の句会では味わえない仲良し俳句仲間です。
ところが会員募集をしてもなかなか入会者が増えません。
そこで、この場をお借りして東雄句会のアピールをしてゆきたいと思います。毎月の佳句をご披露いたすことにしました。いかに我が東雄句会が清く正しくやざかねか・・・をどうぞご覧下さい。
2月投句より
寒晴や秩父遠嶺雲放つ 沙六
山小屋の炬燵に綯ふや藁草履 千秋
今月はまじめな句ばかりでした。
素風
TOPへ戻る
|